冬の陸上競技場情報
陸上競技場を使って行なわれる注目の冬イベント情報
広大なフィールドやトラックを使って、様々なスポーツが行なわれる陸上競技場。冬にはオフシーズンに入るスポーツも多くなりますが、冬ならではの競技やイベントもあるのです。ここでは、注目競技やイベントの内容、開催経緯についてご紹介します。
毎年陸上競技場で行なわれる東京の冬マラソン
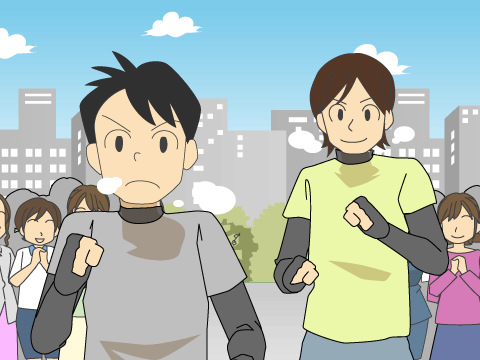
都立大井ふ頭中央海浜公園スポーツの森陸上競技場で、2013年(平成25年)夏の第1回以来、毎年開催されている「大井東京マラソン」。2017年(平成29年)の2月に「大井東京冬マラソン」と題して、冬シーズンに初めて開催されました。種目は、「10㎞」、「10㎞ペア」、「ハーフ」、「ハーフペア」、「フル」、「フルきずな駅伝」の全6種類。「フルきずな駅伝」は4名から10名でたすきをつなぐ種目で、「フルきずな駅伝」以外の種目はすべて年齢別で行なわれています。「フル駅伝」では、1周3,516mを何度も周るクリテリウム(周回)方式で行なわれ、1周ごとに順位や周回数が表示されるのが特徴です。同じく2月に毎年開催されている「東京マラソン」は、世界の主要な市民マラソンとして実力者たちが多く集い、国内でも知る人ぞ知る有名な大会。その「東京マラソン」と同時期に開催されることから、前哨戦として「大井東京冬マラソン」に参加するランナーも多く、熱戦が繰り広げられています。
陸上競技場で冬行なわれる全国高校サッカー
高校生のサッカー部の頂点を決定する、「全国高等学校サッカー選手権大会」。各都道府県の代表として勝ち進んできた48校による、トーナメント形式で行なわれます。毎年1月に決勝リーグ戦が行なわれることから「冬の高校サッカー」とも言われてきました。2017年度で開催96回目となるこの大会は、1910年代から約10年にかけ、第1回から第8回までを関西の学校のみを対象として開催。全国の学校を対象として、予選制で実施されるようになったのは、1926年(昭和元年)の第9回からのことです。以前までは関西の会場がメインでしたが、第55回から決勝大会を首都圏へ移転。予選を突破し準決勝まで勝ち進んできたチームが、「国立霞ヶ丘陸上競技場」で戦うことが許されてきたため「目指せ国立」という目標を掲げて、日々の練習に取り組む高校生も少なくありませんでした。しかし、2019年に開催予定の「ラグビーワールドカップ2019」や、2020年に行なわれる「東京オリンピック」・「パラリンピック」に向けた建替え工事の関係で、第92回大会から会場を変更することとなり、埼玉スタジアムなどで決勝を実施。かつての試合のなかには、後半ロスタイム中に同点PKによって勝敗が左右された決勝戦などもあり、様々なドラマが存在する「全国高等学校サッカー選手権大会」は冬に注目の競技です。
北海道の陸上競技場で行なわれる冬まつり
北海道で唯一の「第一種公認陸上競技場」とされている「厚別公園競技場」は、毎年冬になると「新さっぽろ冬まつり」の会場として使用され、多くの人でにぎわいます。北海道では、「さっぽろ雪まつり」が歴史あるお祭りとして多くの人に知られ有名ですが、この「新さっぽろ冬まつり」は、2017年(平成29年)で12回目の開催を迎えた比較的新しいお祭りです。厚別区が主催となり、新さっぽろ駅の周辺地区のにぎわいづくりや、子ども連れのファミリーに向けた冬の楽しみの提供、地域住民・団体の協働によるまちづくりの実現を目指して実施。雪で作られた滑り台や雪像、かまくらの他に、長靴で楽しむミニスケートリンクやスノーキャンドルづくりなど、北海道ならではのイベントが豊富です。3つに分かれた会場の中のひとつ「厚別公園競技場」では、広大なフィールドを活かしたダイナミックなアトラクションを楽しむことができます。例えば過去には、チューブに乗ってスノーモービルで雪上を引っ張ってもらうスピード感満載の「のりのりチューブ」や、実際にスノーモービルに乗って体験できる「モビール園内ツアー」など、様々なアトラクションが行なわれました。また大人向けの講習会や飲食スペースなども設けられているので、年齢問わず楽しむことができるお祭りとして、毎年厚別区の人をはじめ道内の人や旅行者の人も多く訪れています。



陸上競技の多くは夏前後がシーズンのため、冬は基礎練習や体づくりがメインとなります。この時期は体幹を鍛えるトレーニングや、フォーム改善などに挑戦してみては。近年はスマートフォンもトレーニングの重要アイテムとなりました。
冬のトレーニング方法
冬は体づくりのチャンス

トレーニングが中心となる冬は、走り込みや基礎練習などで体づくりに励む良いチャンスと言えます。不足している筋力を補うことや、痛めた部位のケアをしながら、次のシーズンに向けてメンテナンスを行ないましょう。前のシーズンを振り返り次の目標が定まったら、フォームの調整にチャレンジしてみては。適切に改善できれば好成績を狙うのはもちろん、体への負担を減らす役目も果たします。
いずれにしてもオフシーズンは負荷の少ないトレーニングで、継続させることが大切。バランスの良い食生活も心がけておきたいものです。
スマートフォンやウェアラブル端末を活用しよう
最近ではスマートフォンやウェアラブル端末もスポーツの必需品となりました。例えばスマートフォンのGPS機能で走行距離などの行動記録が測定できるのは広く知られていますが、動画撮影機能はフォームのチェックにも便利です。フォームの分析ができるアプリなら、客観的な判断が得られることもあるでしょう。
また、腕などに着けるウェアラブルコンピュータも身近な存在になりつつあります。スポーツ中の記録を手軽にパソコンで管理できるうえ、消費カロリーや心拍数なども計測でき、健康管理にも役立ちます。
長距離走種目
駅伝
正月に行なわれるスポーツと言えば、駅伝を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。毎年1月1日は、全日本実業団対抗駅伝競走大会(ニューイヤー駅伝)、1月2、3日は東京箱根間往復大学駅伝競走(箱根駅伝)がテレビ中継されており、老若男女問わず、多くの人に親しまれています。
ニューイヤー駅伝は、実業団チームの男子日本一を競う大会です。群馬県庁をスタート・ゴール地点とした7区間、100kmをコースとしており、新年最初の駅伝大会です。一方、箱根駅伝は関東の大学21チームの男子学生対抗で競われます。東京の読売新聞社前を出発し、神奈川県の箱根までの距離を往路5区間、翌日に復路5区間の計10区間、217.1kmを襷でつなぐ競走です。
駅伝の始まりは約100年前、1917年(大正6年)に開催された東海道駅伝徒歩競争と言われています。東京の上野から京都の三条大橋まで、500km以上の距離を3日間かけて襷でつなぎました。海外ではあまりポピュラーな競技ではありませんが、チームで力を合わせてゴールに向かう姿が、日本人の心に響くのかもしれません。
競歩
競歩は、一定の距離を歩く速さを競います。特に男子50kmは陸上競技で一番長い距離を競うため、「最も過酷な陸上競技」とも評されています。厳しいルール規定があり、競技中の失格者が多いのも特徴。両足が同時に地面から離れるとロス・オブ・コンタクト、前脚が接地の瞬間から垂直の位置になるまでに膝を曲げるとベント・ニーという反則が取られます。6~9人の審判員が目視で判定し、違反者には違反を示すパドルが掲示され、これらが続くと失格となってしまいます。
2016年(平成28年)のリオオリンピックでは、競歩50kmに出場していた荒井広宙選手が一度は失格判定となりましたが、抗議の結果、判定が覆り、日本の競歩初メダルとなる銅メダルを獲得しました。
誰でもスポーツが楽しめるように
誰もがスポーツに親しめるよう、様々なカテゴリの競技大会が用意されています。ここでは、主に35歳以上の世代が競技するマスターズ、障がい者スポーツについてまとめました。狙う大会が見つかったら、冬のうちに体づくりを進めておきましょう。
マスターズ陸上(35歳以上の陸上競技大会)
マスターズ陸上とは、35歳以上を対象とした陸上競技を指します。競技は5歳刻みで設定されているため、5年ごとにカテゴリの最若手となり、記録が狙いやすくなります。もちろん記録を追求するだけでなく、生涯スポーツに親しみながら健康維持を目的とした参加者も少なくありません。競技種目は短距離から長距離、走り幅跳びなどのフィールド競技まで様々。競技転向も気の赴くままエントリーできます。
世界マスターズ陸上競技選手権大会は、35歳以上が出場できる隔年開催の陸上世界大会。最近では男性タレントがメダル獲得を目指し、話題となりました。
障がい者の陸上競技大会
障がい者スポーツは第二次世界大戦、傷痍軍人の社会復帰プログラムの一環として取り組んだのが始まりでした。今では軍人の枠にとらわれず、多くの障がい者が分け隔てなくスポーツに親しんでいます。競技は障がいの内容によりクラス分けがされており、誰でもエントリーができるようになっています。同じ短距離走を比べてみても、視覚障がいであれば伴走者と2人で参加し、下半身麻痺などの障がいであれば車いすのレースに出場ができます。
最近はトレーニング技術の向上などにより、より好記録が出るようになりました。ドイツの走り幅跳びの選手、マルクス・レームは、オリンピックに一番近いパラリンピック選手として名を馳せています。2014年(平成26年)に開催されたドイツ陸上選手権では、義足のマルクス・レーム選手が健常者に交じって出場し、見事に優勝。記録はロンドンオリンピックの銅メダルに匹敵するものでした。
大観衆を収容でき、鮮やかに整備されたトラックを持つ陸上競技場。冬は大きな大会での使用は減るものの、マラソンやアマチュア大会などで利用されます。
陸上競技場を使ってみよう

冬の陸上競技場は、フィールド競技や投擲競技の大会の開催が少ないため、個人や団体で使用できる機会が多くなります。陸上競技場を借りる場合は、施設に連絡を取り、申請書を提出するなどの手続きをします。
借りるためには、大会や競技会などを主催し、貸し切りで行なう場合と、個人が自由に使う場合の2つの方法があります。使用料金は施設によって異なりますが、公共施設が多いだけに、それ程高額ではありません。
陸上競技場では、整備されたトラックを走れることはもちろん、ゴールまでの距離感やスタートの確認、トラック表面の感触などを知ることができ、本格的なトレーニングを行なえます。また、団体で運動会やスポーツイベントを開催すると、スケールの大きな敷地でプレーができるので、観客も含めて大いに盛り上がります。
使用にあたって禁止事項が各競技場によって決められており、例えば、スパイクシューズの使用や飲食を禁止していたり、トラックは必ず右回りで使用するなどの注意事項がありますので、必ず守るようにします。また、芝生がある場所では、そのエリアの立ち入りを禁止しているケースもあります。原則として、原状回復が求められており、使用した道具やフィールドは元通りにしなければなりません。雨天の場合などコンディションが悪い場合は、使用できないこともあるので、あらかじめ使用要項を確認しておきましょう。
冬は気温が下がるため、慣れない人にとって屋外での運動は危険を伴います。まず準備運動をしっかりと行なって体を温めたり、マッサージをして筋肉をほぐすなど、競技に入ってケガなどをしないようにしましょう。
市民マラソン
冬の陸上競技で最も盛んに行なわれるのがマラソンですが、近年では一般市民が大勢参加できる市民マラソンが各地で盛況です。タイムや順位を競うマラソン大会とは違い、参加して完走することが主な目的で、人によってはコスプレをしたり、仲間同士で手をつないで走ったりと、楽しみながら走る光景が目立ちます。
参加者は、所定のスタート地点からゴールの陸上競技場などを目指し、自分のペースで走ります。フルマラソンとハーフマラソンなど、各部に分かれて参加できる形式を採っていることが多く、能力によって走行距離を選べるケースが大半です。ゴール地点では完走者にスポンサーから記念品が贈呈されるケースがほとんどです。
市民マラソンは、1980年代後半から徐々に開催されるようになり、2007年(平成19年)の東京マラソンを機に全国の自治体へ波及しました。大会は経済効果も高いため、近年は都道府県主催のものだけでなく、市町村単位での開催も増えています。
ドーピング
冬の陸上競技で注意しなければならないのがドーピング行為で、風邪気味の選手が、風邪薬を飲んだらその中に禁止薬物が入っていることも考えられます。そもそもドーピングは、主に薬物などの化学物質などを体内に取り入れることによって、通常時以上の運動能力を発揮させる行為です。公平なルールのもとで、行なうスポーツの精神に反するだけでなく、副作用が生じるケースもあって世界的に禁止されています。
ドーピングと判断され、禁止される物質は、世界アンチドーピング機関(WADA)によって、毎年10月頃に発表されますが、風邪薬だけでなく、サプリメント、漢方薬の中にも禁止成分が含まれることもあります。ドーピング検査は、競技会で行なうケースと、競技会の外で行なうケースがあります。国際大会などでは、競技の前後に抜き打ち形式で検査を行なうことがあるため、選手は関係機関に外出先を明示する義務が課せられています。
ドーピング問題に関しては、選手はもちろん、コーチなど関係者が禁止薬物をしっかり把握し、選手に伝えることが大切です。
冬はマラソンのシーズンです。スタート地点とゴール地点になる陸上競技場は、ドラマのプロローグとクライマックスが一度に観られるとあって、大会開催日には大勢の人が押し寄せます。ラグビーも陸上競技場を利用して行なわれるスポーツで、冬にはラグビー日本一を決める大会も開かれます。白熱した試合を陸上競技場のスタンドから観戦してみてはいかがでしょう。
マラソン

陸上競技の中でも長距離を走るマラソンは、冬に多く実施されるレースで、各地で様々な大会が開かれます。選手だけでなく市民が参加できる大会も多く実施され、広く親しまれているスポーツです。特に公道を走る陸上競技はマラソンだけで、レースの展開を沿道で誰もが目にすることができます。陸上競技場は、マラソンのスタート地点とゴール地点にされていることも多く、ゴール目前のトラックでの競い合いは、手に汗を握るシーンも見られます。
マラソンの起源は古く1896年(明治29年)にアテネで開かれた第1回オリンピックでは、マラトンからアテネの競技場までの競走として、正式にマラソン競技として発足しました。マラソン競技で走る距離は、42.195kmと決められていますが、マラソン競技が始まった当初は厳密な距離が決められていたわけでなく約40kmとされていただけでしたが、第4回ロンドンオリンピックで、当初、ウィンザー城からシェファードブッシュ競技場までの26マイル(41.843km)で競うことになっていましたが、王妃がスタート地点を宮殿の庭に、さらにゴール地点を競技場のボックス席の前にと指定したため、385ヤード延長され、26マイル385ヤード(42.195km)となり、1924年(大正13年)の第8回オリンピックより、この距離が公式な走行距離と統一されました。なお、当初は男子だけで行なわれていましたが、1979年(昭和54年)に東京国際マラソンが開かれ、初めて女性だけのマラソン大会が行なわれました。
42.195kmを走るマラソンを「フルマラソン」と呼ぶのに対し、その半分の距離である21.0975kmを走るマラソンを「ハーフマラソン」、さらにその半分の距離である10.54875kmを走るマラソンを「クォーターマラソン」と呼び、市民参加の競技会では、これらもよく採用されます。
ラグビーを観戦しよう

陸上競技場は、陸上競技以外にもいろいろな競技で利用されますが、冬に多く利用されるのがラグビーです。ラグビーもサッカーと同じイギリスが発祥で、イギリス国内ではクリケットやサッカーと並んで人気のスポーツです。また、かつてイギリスの植民地だったオーストラリアやニュージーランドなどでも盛んに行なわれ、世界の強豪国としても知られています。日本でも2019年にワールドカップが開催されるなど、ラグビーファンも多く、特に冬季はラグビーの大会が数多く開かれ、脚光を浴びています。
日本におけるラグビーは、主に社会人と学生が盛んで、社会人ラグビーでは全国リーグの「ジャパンラグビートップリーグ」、大学では、大学対抗による「全国大学ラグビーフットボール選手権大会」が有名です。さらに、毎年1月から2月にかけて開かれる「日本ラグビーフットボール選手権大会」は、社会人リーグの優勝チームと大学優勝チームが激突し、ラグビー日本一を決める大会として全国から大きな注目が集まります。
1チーム15人ずつで争われるラグビーの面白さはいろいろありますが、ボールが楕円形で、地面でバウンドしたときにどの方向へ飛ぶのか予想ができないこともひとつです。球技の中で唯一正円でないボールを使う競技であり、予測がつかないボールの動きによりゲームの展開も流動的です。
また、ボールを前へ投げることが禁止されているため、選手はボールを持って走るか蹴るしかないため、その攻防に特徴がうかがえます。スクラムやパス、ラインアウト、モールなどチームとしての連携がとても重要で、相手のタッチライン後方にトライを決めるために、選手個々がそれぞれ役割を果たして連動します。タックルやスクラムなど激しさが目立ちますが、華麗なボール運びや相手を交わすステップなど繊細さも持ち合わせ、試合会場で見ると興奮の度合いも違います。
細かいルールなど分からなくても、一度スタンドでラグビーの面白さを味わってみてはいかがでしょうか。








